2024年、能登半島地震の被災地を巡る政治家の一言が、SNSや報道を通じて大きな波紋を呼びました。
自民党の鶴保庸介参院議員が「運のいいことに能登で地震があった」と発言したことで、被災者や多くの国民から「配慮に欠ける」「政治家として不適切」といった批判が殺到。
なぜこの発言がここまで問題視されたのか?背景にある政策意図や社会の反応、そして政治家の言葉が持つ重みについて解説します。
鶴保庸介氏の発言内容とその背景
参院選応援演説での発言の概要
2024年6月、参院選の応援演説で自民党の鶴保庸介参院議員が「運のいいことに能登で地震があった」と発言しました。この発言は、二地域居住政策の重要性を訴える文脈で述べられたものです。
「運のいいことに能登で地震があった。だからこそ、二地域居住の必要性が分かってもらえる」
—— 鶴保庸介氏(2024年6月、石川県内での応援演説より要約)
二地域居住政策とは?
- 二地域居住とは、都市と地方など複数の地域に生活拠点を持つライフスタイルを指します。
災害リスク分散や地域活性化を目的に、国も推進しています。
二地域居住政策を訴える中での発言意図
鶴保氏は、能登半島地震を例に挙げ、災害リスク分散の観点から二地域居住政策の必要性を強調しようとしました。
しかし、「運がいい」という表現が被災地や被災者の心情に配慮を欠くとして、直後から問題視されました。
なぜ「運がいい」という表現が批判されたのか
被災者への配慮を欠いた発言と受け止められた理由
- 「運がいい」という言葉は、被災者の苦しみや被害の深刻さを軽視していると受け取られやすい表現です。
- 特に能登半島地震は死者・行方不明者を出し、今も多くの住民が避難生活を余儀なくされている状況でした。
- 政治家としての立場を考えれば、なおさら慎重な言葉選びが求められる場面でした。

被災地や被災者への配慮が欠けていると受け取られる発言は、社会的な信頼を大きく損ないます。
SNSや報道での社会的反響と批判の広がり
発言直後からSNSやニュースで批判が急速に拡大。
- 「被災地への冒涜」「政治家として不適切」など厳しい意見が相次ぎました。
- X(旧Twitter)上でも多くの批判が投稿されました。
こう言う発言する人って毎回思うんだけど、どういう育ち方したらこんな人間に育つのか毎回不思議に思う。— しんちゃん (@BeatAngel200208) July 8, 2025
咄嗟に言葉を選び間違えることくらい誰にでもある。この部分だけ切り取るほうがよっぽど悪意ある。
2拠点居住という政策を進めているところに、まさにその必要性を痛感させる能登地震が起こったと言いたいのでしょう。— 政治について語るアカ (@Baikoku_Tobatsu) July 8, 2025
能登の地震を運がいいこと?
どれだけの被害が出て、今も苦しんでいる人がいるのを知っていての発言だったのでしょうか。ありえません— mimi先生|1児の母 (@mimi_sensei_) July 8, 2025
人ってね、熱くなって喋ると本性が出るんだよ
平常時は出ない本性がね
完全に思ってるよね?運よく能登地震が起きたって— ポップコーンs (@moviemiruhito) July 8, 2025

SNSでの批判拡大は、政治家の不用意な発言が瞬時に全国へ拡散する現代社会の特徴を象徴しています。
鶴保氏の発言撤回と謝罪の経緯
撤回・謝罪に至った背景
- 世論の批判を受け、鶴保氏は発言を撤回し、公式に謝罪しました。
- 「発言の意図が誤解を招いたこと、被災者や関係者に不快な思いをさせたことを深く反省している」とコメントしました。
「被災者の皆様に不快な思いをさせたことをお詫びします」
—— 鶴保庸介氏(公式声明より要約)
発言意図の説明と今後の姿勢
- 鶴保氏は、あくまで二地域居住政策の必要性を訴えるための例示だったと説明。
- 今後は「言葉選びに一層注意し、被災者や国民の感情に配慮した発信を心がける」と表明しました。
二地域居住政策と能登地震の関連性
二地域居住が注目される政策的意義
- 二地域居住政策は、災害リスクの分散や地方活性化、人口減少対策など多面的な意義が注目されています。
- 2023年の国土交通省調査によると、二地域居住を希望する人は年々増加傾向にあります。
| 年度 | 二地域居住希望者数(推計) |
|---|---|
| 2021年 | 約80万人 |
| 2023年 | 約100万人 |
能登地震を例に挙げた理由とその影響
- 能登地震は、地域社会に大きな被害をもたらしました。
- 鶴保氏はこの現実をもとに、災害時のリスク分散策として二地域居住を訴えた形ですが、発言の仕方が適切でなかったため、政策の意義そのものにも一時的に疑念が生じました。
他の「不適切発言」事例との比較
| 年 | 発言者 | 問題発言 | 社会的反響 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 鶴保庸介 | 「運のいいことに能登で地震があった」 | SNS・報道で批判、謝罪・撤回 |
| 2018 | 今村雅弘(いまむら まさひろ)元復興大臣 | 「被災地は自己責任」 | 強い批判、辞任に発展 |
- 2018年に社会的な批判を集めた「不適切発言」の代表例が、今村雅弘元復興大臣によるものです。
- 今村元大臣は、東日本大震災や原発事故の復興政策を担当していましたが、2017年4月に原発事故の自主避難者に対し「自己責任」「裁判でも何でもやればいい」と発言。
- さらに、「(東日本大震災が)まだ東北で、あっちの方だったから良かった」とも述べ、被災者や世論から強い批判を浴びました。
- 報道やSNSで大きく取り上げられ、最終的に発言の責任を取り辞任しています。
政治家発言の社会的影響と今後の課題
公的立場の発言に求められる配慮
- 政治家の発言は社会に大きな影響を与えます。
- 特に被災地や弱者に関わるテーマでは、言葉の選び方一つで信頼や共感を失うリスクがあるため、最大限の配慮が求められます。
政策推進への信頼確保と慎重なコミュニケーションの重要性
- 政策の正当性や有効性を伝える際にも、国民の感情や現場の実情に寄り添った説明が不可欠です。
- 今回の事例は、慎重なコミュニケーションの重要性と、信頼確保の難しさを改めて浮き彫りにしました。
まとめ|今回の発言が示した教訓と今後の対応
今後、政治家にはより一層の配慮と責任ある対応が期待されます。
今回の一件は、政治家の発言が社会に与える影響の大きさを改めて示しました。
政策の意義を伝える際も、被災者や国民への配慮を忘れず、慎重な言葉選びと説明が求められます。
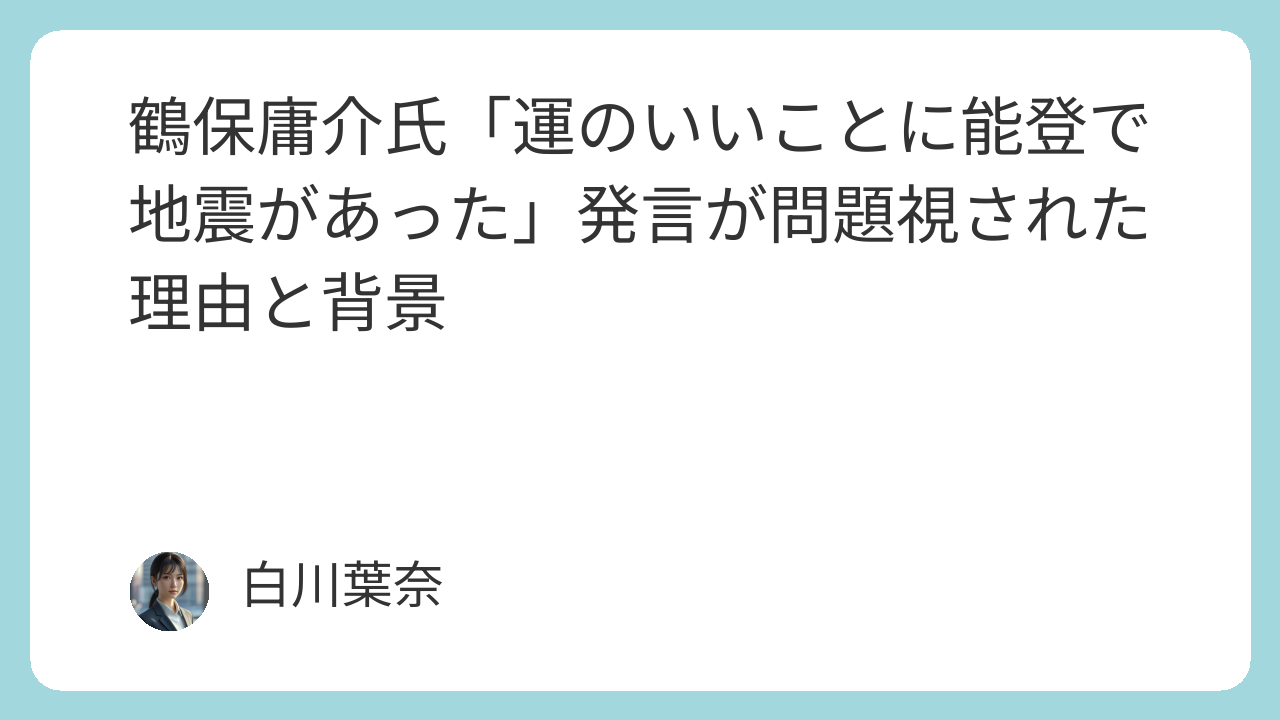
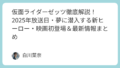
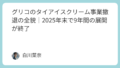
コメント